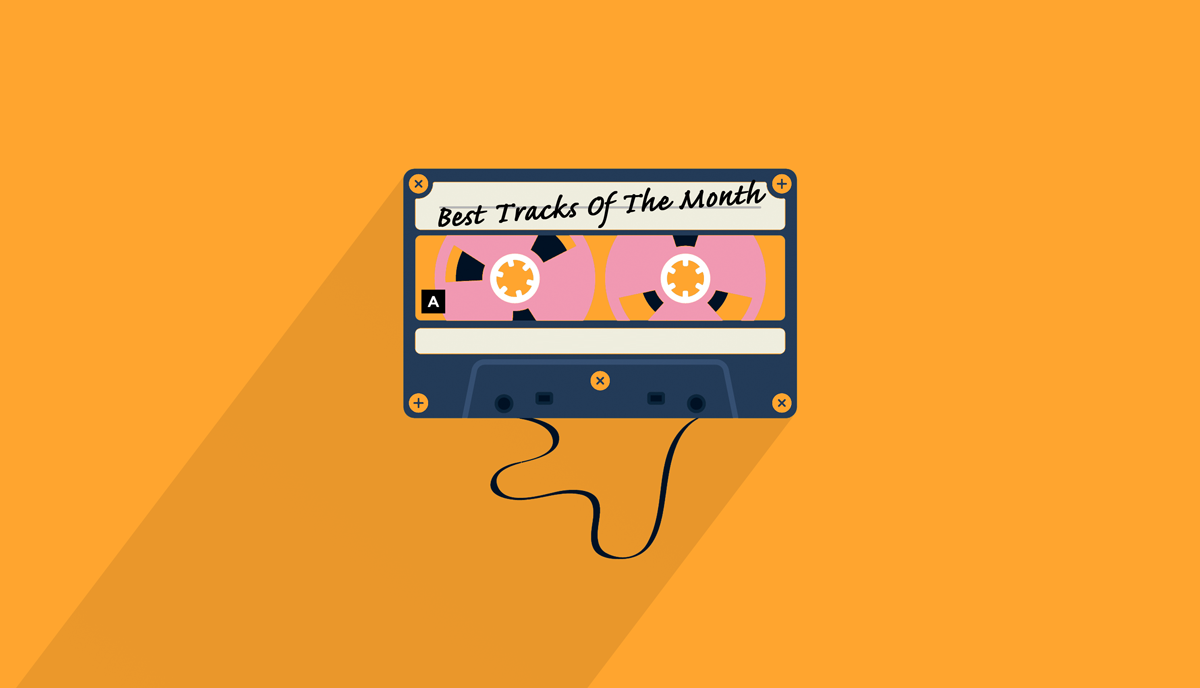BEST 14 TRACKS OF THE MONTH – September, 2022
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
brakence – 「caffeine」
ミントガムを噛みながらアイスシャワーを浴びたように強烈なdigicore調のビートに乗せて、オハイオの20歳、brakenceは自身の音楽のチージーさとそれによる成功を吹きつける。ビートはさらにジャージー・クラブとトラップとの両極端にピッチを変化させ、リリックも脈絡のない思考と絶望とを対比させていく。MVにおけるゲームへの言及は楽曲の主題の一つでもあり、性急なサウンドやタイトルと紐づいて、不安定な若者のリアリティを映し出す。ラストに彼は、自分の生まれ年に発売されたゲーム機に引っ掛けながら、キャリアの今後への不安を告白する。「ゲームが上達(advanced)しすぎたんだ、ボーイ、俺には時間が必要さ」。(髙橋翔哉)
Hazey – 「Bringing It Back」
UKドリルの勢いは止まる所を知らないのだろうか。TikTokから火がつきUKチャートでは11位にまで上り詰めた「Packs and Potions」は日本のクラブで耳にする機会も多かった、スカウス(リヴァプール)のヤングガン、Hazeyの新曲。ヴォーカル・サンプルのループが特徴的なバイレファンキ風のトラックに独特な声質で繰り出すフロウが絡み合って生まれるダンサブルなグルーヴは秀逸。ちなみに「Packs and Potions」をプロデュースし、「Bringing It Back」にもクレジットされているSphero Beatzは、C.O.S.A.とRalphによる「Pop Killers」のトラックも手がけている。(高久大輝)
Paramore – 「This Is Why」
フィービー・ブリジャーズ、ジュリアン・ベイカーらを中心に、近年インディー・ロックの一潮流となったフィメイル・シンガーソングライターたちがこぞって音楽的ルーツとしてその名をあげ、自らも意欲的なソロ作品を続けてリリースしてきたヘイリー・ウィリアムス。彼女がヴォーカリストを務めるパラモアがついに5年ぶりとなるニュー・アルバムを来年2月にリリースする。今回発表された本曲「This Is Why」は、ポスト・パンク・テイストのタイトなドラム・ビートと、ギター・カッティングが光るクールな一曲。前作『After Laughter』(2017年)でも明確だった、もはや2000年代のストレートな“エモ”とは距離を取った今のパラモアの全体を早く見回したい。(尾野泰幸)
Men I Trust – 「Billie Toppy」
モントリオールの3人組バンド、Men I Trustによる今年2作目のシングル曲は、これまでのドリーム・ポップ路線からニュー・ウェイブへ大きく転換する意表をつくナンバー。ポストパンク〜ダークウェイブ直系のクリーンギターと粘っこいベースラインは久しぶりに胸が高鳴った。エマニュエルの甘い歌声に内包される不穏なアンサンブルは、ジョイ・ディヴィジョン好きなら小気味よさを覚えるはずだ。新たな遍歴をたどるサウンドは、効果音のようなコーラス、80年代風の艶やかなシンセなどを細かく散乱させた、解放的な展開になっている。ここまでクロスオーバーな変化を遂げると、彼らの分岐点とも言える1曲なのでは。今後の動向に注目したい。(吉澤奈々)
Weyes Blood – 「It’s Not Just Me, It’s Everybody」
11月18日に発売される新作『And In The Darkness, Hearts Aglow』からのこの先行曲は、前作『Titanic Rising』(2019年)で得た圧倒的な評価をさらにその先へと導く重要曲。“その先”とはスタンダードなポップスとしての矜持。スタンダードの定義は日々進化/変化しているが、サンフランシスコ出身のナタリー・メーリングは敢えて古典的なポップスの再定義に賭けている印象がある。バカラック/デヴィッドがカーペンターズやディオンヌ・ワーウィックに提供した曲の持つ、感情が深く重なり、その複雑な情緒が甘美なアレンジを引き出したあのポップスの芳醇さ。彼女がそこに“回帰”ではなく“未来”を託した理由……それはニュー・アルバムの到着を待つこととしよう。(岡村詩野)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
Daniel Avery (feat. HAAi) – 「Wall Of Sleep」
11月リリースのダニエル・エイヴリー『Ultra Truth』から新曲。HAAiが以前運営していたレーベルのパーティーで2017年に共演したことから交流が始まったようだ。アルバムのテーマは暗闇から逃げないことらしい。他にもケリー・リー・オーウェンスをはじめロンドン・アンダーグラウンドを牽引するアーティストが参加する中で、アルバムの美学を担うのがこの曲なのはHAAiの楽曲が持つ解放感をダニエルが必要としているからかもしれない。浮遊感のある轟音の中、威厳に満ちたキックと《FLAU》を連想するような繊細なコーラスが同居するドラムンベース〜ダブステップ。アルバムを通して聴いたとき、本楽曲がどう聴こえるのか楽しみだ。(佐藤遥)
DannyLux – 「Respuestas」
コールドプレイのメキシコ・ツアー2022のオープニング・アクトにも抜擢された、弱冠18歳のシンガー・ソングライターであるDannyLuxの最新EP『Limerencia』からの一曲。カリフォルニア州パーム・スプリングス出身のチカーノだ。EPタイトルは、一方的に執着してしまう自制できない恋心の状態を示すそうで、このEPを通じて徐々に冷静になっていく物語だ。スペイン語の発音はどこか情熱的だが、この楽曲のアコギでしっとりと進む様は、過去を冷静に振り返っているかのようだ。あまり手を加えていないシンプルな構成のため、聴いていてどこか懐かしさと共に哀愁が漂う。ギター一本で聴かせてしまう注目のメロディメイカーだ。(杉山慧)
Hannah Jadagu – 「Say It Now」
テキサス出身、ニューヨーク在住、《Sub Pop》が送る20歳のニューカマー。ベッドルームでiPhone 7とiRig、ギターを使いひとりで録音した2021年のEP『What Is Going On?』で黒人女性としての経験やティーンのメンタルヘルスについて率直に綴った彼女はいま、かつての恋人との関係に思い巡らせ、より率直であろうと決意する。自らの内面を深く覗き込む洞察力と、ポップソングを書くことに意識的であることは相反しない。デリケートではあるが確かな意思を感じさせるヴォーカルと天に昇るギターの響きで、3分40秒が終わると遠くに連れていかれたような開放感が満ちる。敬愛するクレイロやビーバドゥービーに連なる逸材。(駒井憲嗣)
Jamie xx – 「KILL DEM」
今年2作目となるソロ楽曲は、ダンスホールのクラシック、カッティ・ランクス「Limb By Limb」をカットアップしたハウス・ミュージック。カリブ諸国の文化を祝い、ロンドンのストリートに多数のサウンドシステムを組んで開催されるノッティングヒル・カーニバルにインスパイアされたという。シリアスなトーンに、ボンゴのような楽器や偶数拍を強調するリズムパターンを織り交ぜ、エネルギッシュで洗練されたこの曲が湛えているのは、カルチャーへのリスペクト。原曲でも耳に残る“See me me me〜”の16分音符が並ぶフレーズを活かした部分には中毒性があるが、10代の頃からカーニバルに足を運んでいた彼がその場で感じていた魅力の表出なのかも。(佐藤遥)
Say She She – 「Pink Roses」
人種の異なる3人の女性ヴォーカルがリードするブルックリンの7人組によるナンバー。シックの「Le Freak」の歌詞“C’est Chi Chi”からバンド名を取ったとあってヴィンテージなディスコ・ファンク~ソウルを聴かせるが、特徴的なのは白人・黒人・南アジア系というメンバーのルーツと感性がミックスされることで生まれているのであろうサイケ感。10月リリースのデビュー・アルバム収録のこの曲は、ソウルの甘いハーモニーに、ゲーム音楽のようなチープなシンセ、ポスト・パンク風のスカスカのビートを掛け合わせており、壊れたラジオから流れてきたかのような異世界感は中毒性が高い。もともと、これとは別のインド風アレンジの楽曲から火がついたグループなので、昨今の南アジア・ブームとの共振も今後見せるのかにも注目したい。(井草七海)
Shabason & Krgovich – 「In The Middle Of The Day」
ニコラス・ケルゴヴィッチが2018年に発表したアルバム『Ouch』にジョセフ・シャバソンが参加して以降、微睡みを誘うような二人のサウンドは驚異的なマリアージュを発揮した。ダブルネームでの新作『At Scaramouche』(2020年のクリス・ハリスとのトリオ名義作『Philadelphia』と合わせた日本独自2枚組として10月7日に発売)からの先行曲「In The Middle Of The Day」は、そのマリアージュがニューエイジ・ミニマム・ファンクとでも言いたくなる(というより、としか言い表せない)極上のポップスとして完結したことを否応なしに感じさせてくれる。堅牢なベースラインとブレイクビーツの間に滑り込むシンセサイザーとサックスの軽やかさは、新世代(ニューエイジ!)のスタンダードの誕生を予感させてやまない。(風間一慶)
Smino – 「90 Proof feat. J. Cole」
漢字一文字で表すならば“妖”といったところだろうか。なんかもうベースからして(もちろん良い意味で)いやらしくて、スミノの声もいっそういやらしく響くというものだ。「愛されることに慣れてきているんだ」と打ち明けるスミノはマリファナを巻き、友人からの誘いに屈し、この歌をバックに情事に興じる。人目につかないようこっそりと。同じくひっそり暮らす客演のJ. コールのヴァースは幾分真面目すぎる内容だが、メロディのセンスが印象を和らげている。10月にリリースが目される3作目のスタジオ・アルバム『Luv 4 Rent』からのリード・シングルか。10月2日に31歳の誕生日を迎えたスミノから目が離せない。(奧田翔)
壞特 ?te – 「Self Love」
本名も明かさず、顔出しもせず、徹底的にミステリアスなイメージ・プロモーションを行う壞特 ?teの新曲は「Self Love」。中国語・英語・スペイン語を操る歌詞の無国籍感と、レコードのスクラッチ音や古いラジオを通したような意図的なヴィンテージ風のサウンドメイクで、時代や国を超越した独特の存在感を示していた彼女だが、1年ぶりのシングルで高らかに謳ったのは自己肯定の素晴らしさである。自らのイメージを模したという、このいじらしいイラスト!何よりも彼女が「自ら」を歌い出したこと、何の理由もなく、ただ自分を愛していると、そのハスキーで艶のある声でしなやかに歌い上げる姿に感動を覚えずにいられない。(Yo Kurokawa)
スカート – 「架空の帰り道」
ドラムブレイクから始まるイントロが鳴り出した瞬間に、思わずオッと声が出てしまった。アルバム『トワイライト』(2019年)以降、エヴァーグリーンなフォーク・ロック路線が続いてきたスカートが久々に放つファンキー・チューン。軽快にうねるビートに絡みつく佐藤優介のエレピが最高に気持ち良い。さらにそこからシームレスに繋がりつつ、パッと視界が開けるサビの解放感、わずか1分半でワンコーラスを完結させ、楽曲のスウィートスポットを聴かせきってしまうミニマルな構成に、コンポーザーとしての手腕を感じさせる。この曲はTVドラマの主題歌とのことだが、制約すらも楽曲の魅力へ転換させる澤部渡の頼もしさ。来たる新アルバムへの期待が高まる。(ドリーミー刑事)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Sho OkudaYo KurokawaHaruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiNana YoshizawaIkkei KazamaDreamy DekaShino OkamuraKei SugiyamaNami IgusaDaiki TakakuYasuyuki Ono