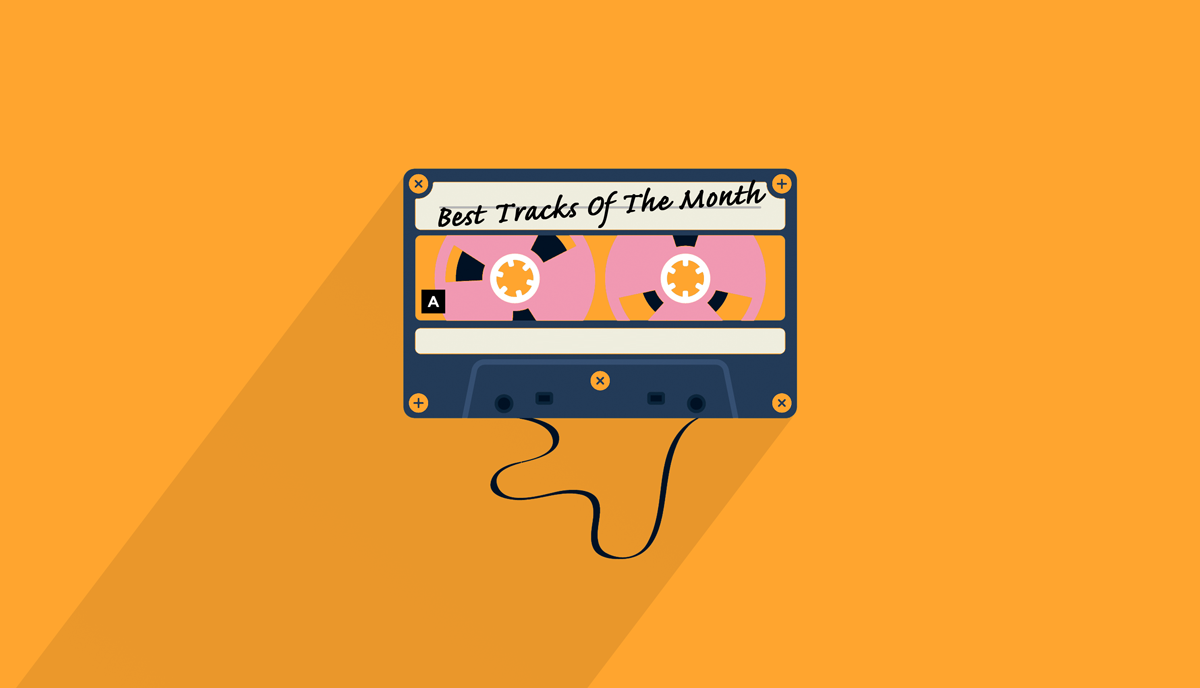BEST 14 TRACKS OF THE MONTH – Sep, 2023
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Ava Mirzadegan – 「Book Song」
ジョアンナ・スタンバーグに出会った時にも似た手応えを感じている。フィラデルフィアのシンガー・ソングライターの、11月3日リリースのデビュー・アルバムからの先行曲。フォーク音楽ではあるものの、ジョアンナのような朴訥とした無垢さとは少し違い、少しアンビエントが入ったサウンド指向で、歌とメロディのあるスタイルながら、アコースティック・ギターのボロンボロンとした音色とその響きを捉えた作風がたまらなく心地いい。“本の歌”というタイトルもこの時期にピッタリだし、書店でロケをしたMVも素敵。来るアルバム・タイトル『Dark Dark Blue』からはジョニ・ミッチェルを思わせたりも。そのジョニ、タラ・ジェーン・オニール、加藤りまあたりが好きな方にぜひ聴いてほしい。(岡村詩野)
BIA, Pa Salieu, ODUMODUBLVCK – 「CHATTY」
『Sisterhood of Hip Hop』への出演などでも注目を集めてきたマサチューセッツ州出身のラッパー、BIAが7月にリリースしたEP『Really Her』に国境を超えたコラボレーションを加えて“INTEL DELUXE”としてリリース。そこに収録されたこの「CHATTY」にはガンビアにルーツを持つUKのラッパー、パ・サリューとナイジェリアはアブジャを拠点に活動するコレクティヴ、Anti World GangstarsのメンバーであるODUMODUBLVCKが参加。アフロビーツ的な軽快でエネルギッシュなビートにそれぞれのフロウが心地よく乗ったダンス・チューンで、そんな中でもBIAは他の2人に劣らず存在感を示している。あるインタヴューでは自身を“超自信家”と称していた彼女は、コラボレーションを通して改めて自らの個性を浮き彫りにしただろう。(高久大輝)
UNIVERSITY – 「Notre Dame Made Out Of Flesh」
英国3人組による3曲目のリリース。かつてのUSポストハードコアを彷彿とさせるザクザクいうギターが跳ねるドラムとともに、焦燥感に駆られるようにまくし立てるように推進していく。サウンドはカラッと乾いているが、リリックはエモーショナル。「君に会えたらいいのにいい!/俺の声が聞こえたらいいのにいい!」。さらに過去と未来の可能性を否定。諦念とコンプレックスが発露した言葉は、俺と君のセカイを結びはしないけど、ロックは復権(?)したらしいが彼らのような“インディー・ロック”・アクトは報われず各地で孤軍奮闘するしかない現状を映し出したかのようだ。近年ノイジーで刹那的なオルタナ・サウンドが思い出されつつあることを象徴する一曲。(髙橋翔哉)
Yumi Zouma -「KPR」
ニュージーランドを拠点に活動するインディー・バンド、Yumi Zoumaの新曲に心が躍った。Yumi Zoumaはドリーム・ポップの中でも、特有の甘いメロディーや洗練されたシンセのアレンジをリスナーに印象づけてきたと思う。しかし、12月リリース予定のEPからのファースト・トラック「KPR」はギターを主軸に力強くバンド・サウンドを鳴らしている。ギターをはじめ音色の厚みは増し、緻密なアレンジもバラエティ豊かになった。シンプソンのシャウトからギターのノイズへの繋がり、ドラムとクラップが入れ替わる構成など冒険心のある楽曲に惹き込まれる。東京で撮影されたという、鮮やかなLEDスクリーンに囲まれるMVも必見。(吉澤奈々)
SOFTTOUCH – 「焚火」
2000年代前半、アジアン・カンフー・ジェネレーションと同時期に《UNDER FLOWER RECORDS》へ所属し、近年では後藤正文が主宰する《only in dreams》から作品をリリースしてきたオルタナ/パワーポップ・バンドによる最新楽曲。バンドの特徴であるエモーティヴな泣きメロを主軸とした真っ直ぐなオルタナティヴ・サウンドに、社会を生きる上で生じるコミュニケーションや通念への違和感を抽象度をあげて表現したリリックは本曲でも健在。ロック・バンドにおける成功や失敗の基準を規定することは単純ではないけれど、結成から長い時間を経たバンドにしか出せない抒情と輝きは確実にあるのだとソフトタッチの音楽を聴く度に思う。(尾野泰幸)
霊臨 – 「ROBOT」
:Plueが手がける哀しいくらいお天気なビートのせかせかした四つ打ちが終わるころ、僕はまだ人間らしいやさしさを保っていられるだろうか。「123456/前進するのが大事よ(T ^ T)」。言われてできたらやってるわ。でも実際はその場で足踏み、というか地団駄? また泣いちゃうぜ。機械のように感情や疲労を忘れることができたなら、きっと陽気に暮らせるはずなんだ。感情から逃れられる喜びと、人間らしくありたい悲しみとに分裂するように、センチメンタルな霊臨のリリシズムは相変わらず。社会の一部としてニンゲンとして肉体を駆動するのはつらいけど、同シングル収録の「Glasses」を聴いて笑いましょう。ほんっとにくだらない!(髙橋翔哉)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
aus, Gutevolk, LI YILEI – 「Steps (Li Yilei Remix)」
テープ・デッキを動かす音に続いて聴こえるのはノイズ、あたたかくてさみしい音による旋律、おぼろげな歌声。「Steps」はausの個人的なストーリーが中心にある『Everis』の楽曲で、Li Yileiは「Steps」のステムデータを繰り返し聴くことで過去の記憶からのフィールド・レコーディングのような質感を感じ取ったという。Liの『之 / OF』は、雄大な時間の流れとパーソナルな感情の機微をつなぎ合わせ、緊張や安堵がより親密に浮かび上がる作品だった一方で、個人の記憶にある共通項とも言えるものにフォーカスした本楽曲は、浮遊し全ての時間の流れを眺めているよう。10月末リリースのリミックス・アルバム『Revise』に収録。(佐藤遥)
Blondshell – 「Street Rat」
Blondshellは、LAを拠点に活動しているサブリナ・タイテルバウム(Sabrina Teitelbaum)のソロ・プロジェクト。ニルヴァーナやスマッシング・パンプキンズなどから影響を受けたサウンドと、怒りを曝け出す姿勢に、グランジの新世代アイコンとして注目を集めている。デビュー作『Blondshell』完成直後に出来た楽曲で、デラックス盤に追加収録された新曲。やめられない行いがもたらす結果として、自分の周りで起こる問題、そのメタファーとしてドブネズミと表現しているのではないだろうか。でもこのサウンドで歌われると、そうした部分をただ否定するのではなく、自分らしさとはそうした部分と切っても切り離せないモノだという含みも感じられる。(杉山慧)
Devendra Banhart – 「Fireflies」
一聴して「クラブのストロボの明滅と対照的な静けさ」のような映像が不思議と浮かんだが、公開されたMVの人影が疎らなダンスホールとネオンが醸す停滞した寂しさに、どこかイメージがリンクした気がして驚く。デヴィッド・リンチ『ツイン・ピークス』のテーマソングのような静けさの中、ミニマルに反復する音がしんしんと積み重なり、同時に立ち現れる「深さ」。それは冗長に更けていく一夜のように、あるいは深海に身を浸していくように、精神がゆっくりと沈んでいくのが心地良い。今回のプロデューサーであるケイト・ル・ボン(Cate Le Bon)の『Pompeii』におけるニュー・ウェイヴ的質感の影響が全面に出ながらどこか神秘性も帯びている。4年ぶりのニューアルバムのムードを明示する一曲。(寺尾錬)
Emma Tricca & Bridget St John – 「Rubies」
針を落とした(再生ボタンを押した)瞬間、ため息が漏れてしまった。2018年のアルバムではジュディ・コリンズとのコラボレーションを果たしているエマ・トリッカは、この曲が書けたとき、ブリジット・セント・ジョンのヴォーカルしか思い浮かばなかったという。果たして、ドラムスのスティーヴ・シェリーらバンド・メンバーによるサポートのもと、それぞれのスタンスを貫いてきたシンガー・ソングライターの邂逅が実現。ベス・オートンの最新作でも印象深かったジェシー・チャンドラーがフルートで参加しているから、ということもあるが、『Weather Alive』(2022年)の隣に置きたいたおやかさ──ただしノスタルジーとは無縁の──に溢れている。(駒井憲嗣)
Jalen Ngonda – 「That’s All I Wanted From You」
ジェイレン・ンゴンダはワシントンD.C出身で《Daptone》に所属しながらも、現在は英国を拠点にしている。この曲を一聴してわかるように、モータウン直系のヴィンテージ・ソウルが彼の音楽スタイルであり、芯の通ったハイトーン・ヴォーカルもまさにマーヴィン・ゲイを理想としていることが伺える。このシングルを含む、9月リリースのデビュー作『Come Around and Love Me』はまさにソウル黄金期のヴァイブがよみがえっており、若者によるノーザン・ソウル再評価が高まりつつある英国を活動の場に選んだのは正解と言える。(油納将志)
luna Falcão, Xenia França – 「Estrela」
“先祖らのテリトリーで行われていたディアスポラ的な音楽の邂逅に基づくサウンドによるコンテンポラリー・ブラック・ミュージック”。デビュー作の発表を控えるブラジリアン・シンガーのluna Falcãoは壮大なプランを掲げている。先行シングル「Estrela」では、昨年リリースされたアルバム『Em Nome da Estrela』でカンドンブレとエレクトロニカをミックスし、ルーツの昇華を測った鬼才、 Xenia Françaを迎えた。柔らかなフェンダーローズと、緻密かつ厳密に重ねられるビート。歌が捧げられるのは、ヨルバの伝統に基づいた女性信仰にまつわるオリシャたち。両者の作品に参加しているプロデューサー/レコーディング・エンジニアのPipo Pegoraroや腕利きのプレイヤーチームであるA Timelineらの働きも見逃せない。(風間一慶)
Masami Takashima – 「Kotoba」
香川を拠点に活動するMasami Takashima。90年代より音楽活動を始め、昨年はエマーソン北村とコラボレーション・シングルを発表した彼女の7thアルバムがとてもいい。「Kotoba」は作品の冒頭を飾るアンセム。ダウンテンポ、ダブ、レゲエ、R&Bへと変幻するプログレッシヴな展開にのせて、どんなに言葉を重ねても雲を掴むようにすり抜けてしまうもどかしさを歌った楽曲だ。ニュー・ウェイヴ・バンドでも活動しているという背景からも頷ける明暗を折衷した大胆なアレンジは、様々な角度から1つの対象を見つめているようにも思え、何かに対して安易な答えを導き出すことを拒絶し、未知をさまよう行為のように感じられる。(前田理子)
Sampha – 「Only」
自分のonly youとは何なのか。この「Only」では、それは恋人でも親でもなく、ひとりに宛てたものではない、もっと大きな彼の信念を思い起こさせる存在に思える。その信念は、愛なんて不確実なものよりも、自身を容認してくれるらしい。そこに説得力を持たせている、ミニマルで張り詰めている曲調のビートを進めているのは、ブレイク部分のようなハイハットで、時の焦燥を感じる。常に更新するべきキャリアであるのか。「Only」が響き渡るフックはメロディアスにうたわれており、私はここでいつも残響の中に落ち着いてしまう。信仰心というのはそうか、ここでonly youの対象が現れたのだ。その張り詰めた感覚からの解放が今の彼ではないだろうかと思わせてしまう、アルバム『Lahai』を通して、前作からの踏み跡を聴くのを心待ちにしている。(西村紬)
柴田聡子 – 「Synergy」
ドラムに浜公氣(mei ehara、Lantern Parade等)ベースにまきやまはる菜、そしてギターとプロデュースに岡田拓郎という新体制での新曲。ブレイクビートで始まるイントロは名曲「雑感」を彷彿とさせるが、代名詞のフォーキーな手触りは後景化。J・ディラやアニマル・コレクティヴを手がけたDave Cooleyがマスタリングした現行R&Bと並走するハイファイ感と、それを咀嚼しユーモアすら漂わせるオリジナルな音像に揺さぶられる。パーカッシヴなヴォーカルが描くのは、孤独の極北へ到達した前作『ぼちぼち銀河』の世界を突き抜けた、個と個が共に前を向く瞬間か。新章到来の期待感を高める一曲。(ドリーミー刑事)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Haruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiRiko MaedaNana YoshizawaIkkei KazamaRen TeraoTsumugi NishimuraDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoKei SugiyamaDaiki TakakuYasuyuki Ono