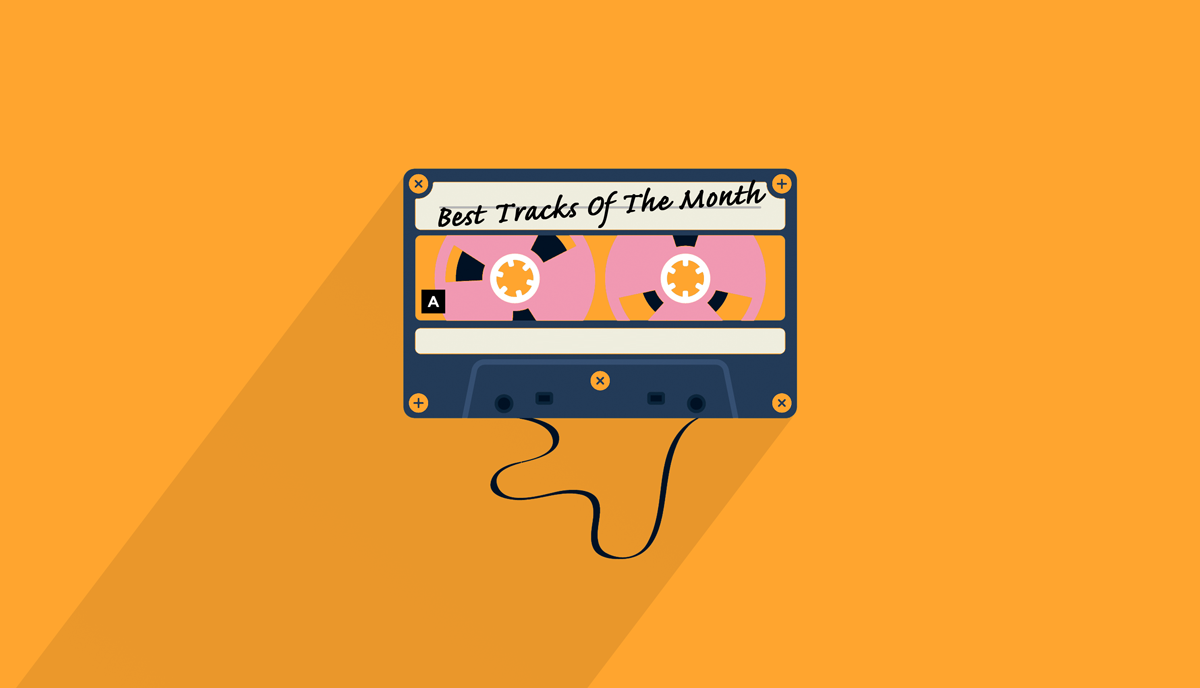BEST 14 TRACKS OF THE MONTH – Nov, 2023
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Babebee – 「A PROPHECY ON LOVE」
アトランタを拠点に活動する韓国系アメリカ人のシンガー・ソングライター/プロデューサー、Babebee(読み方はBaby)による中毒性のあるナンバー。ゆらゆらとギターのエコーが行き交うなか、80年代のゲームサウンドを思わせるビートが意表を突く。他にも、突如スロー・テンポに切り替わる展開などベッドルーム・ポップとテクノポップを自由に横断するかのよう。異なる領域の音質をアクセントにした楽曲は実験性に富んでいる。というのも、《Epitaph Records》 からのリリースとなるEP『A PROPHECY』は自己受容や失恋の傷を癒す作品だそうで、Babebeeのイマジネーションを彷徨するような内容に納得。(吉澤奈々)
Bolis Pupul – 「Completely Half」
昨年シャーロット・アディジェリーと素晴らしい共作アルバム『Topical Dancer』をリリースした、中国とベルギーのハーフであるボリス・ププルが2024年にソロ・デビュー・アルバムを届けてくれることになった。アルバムのテーマは、記憶、喪失、家族、そしてそれらすべてと折り合いをつけ、和解すること。この先行曲では、デトロイト・テクノとシカゴ・ハウスが音楽的ルーツというボリスの指向性をよりカジュアルかつチープにし、アジアのアイデンティティを伝えるメロディを、タイトルさながらに半々に掛け合わせている。ちょっと80年代の《Les Disques du Crépuscule》の作品みたいなメランコリーとユーモアを感じるのはベルギー出身だからか?(岡村詩野)
Mo Troper – 「Citgo Sign」
オレゴン州ポートランドを拠点として活動するシンガー・ソングライター、モー・トロパーによるジョン・ブライオンのカバー・トラック。ジョン・ブライオンといえば、近年ではフランク・オーシャンやビヨンセ、ブレイク・ミルズ、ジャネール・モネイなどの作品でプロデュースや演奏参加し、数々の映画音楽も制作するなどマルチに活躍するミュージシャンとして知られるが、活動初期にはジェリーフィッシュのジェイソン・フォークナーと共にザ・グレイズというバンドで活動するなど、パワー・ポップが音楽的ルーツにある人物でもある。ブライオンのオフィシャル・リリースはされていないがインターネット上で流通してしまっているデモ・トラックにあたる本曲は、ジャングリーなギターが導くビートルズ・ライクなポップ・センスの光る佳曲。ローファイな録音もまるで原曲をリスペクトしているよう。(尾野泰幸)
Peggy Gou & Lenny Kravitz – 「I Believe In Love Again」
ビヨンセ「BREAK MY SOUL」に対するアンサーといえようか。ユーロ・ハウス的なサンプルに「よいしょ、よいしょ」ともたついたビートを耳になじませるだけでいい。レニー・クラヴィッツの高く伸びやかに響く享楽的なヴォーカルに、「今夜、君は知っているでしょう……探していたものが、きっと見つかる……」と囁きかけるペギー・グーの声とともに、アナタの体は“higher place”へと導かれるはずだ。「(It Goes Like) Nanana」のヴァイラル・ヒット以降、グーがトロピカルな夏を名残惜しんでいるようにも聴こえるが、むしろ時代が’90sフロア回帰によって彼女を迎えにきたと言うのが正解だろう。(髙橋翔哉)
Ryder, Skepta, Dré Six – 「All Alone」
待ちに待ったスケプタの新曲はハル出身の若きプロデューサー、Ryderによるメランコリックなビートと、シンガー・ソングライター、Dré Sixの美しい歌声と共に届けられた。スケプタは落ち着いたトーンで「昔は金のために祈ったのを覚えている、今は子供が成人するまで生きていることを祈っているのさ」と彼の生きてきた/生きている世界を綴っている。スケプタ「Bullet From A Gun」のMVなども手がけているディレクター、Duncan Loudonとスケプタによる哀愁を帯びたMVと合わせて聴いて欲しい。なお、この曲も入ったスケプタとRyderによるEP『48 Hours』に収録されているいくつかの曲名に付く“#skeptacore”はスケプタの作品にインスパイアされたリフィックスをプロデューサーたちが作り上げたものを指す、Ryderによる造語らしい。TikTokやSoundCloudでぜひ検索を。(高久大輝)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
Bruno Berle – 「Tirolirole」
昨年7月に英《Far Out Recordings》よりデビュー・アルバム『No Reino Dos Afetos』を発表し、ノスタルジーを誘う穏やかなサイケデリック・フォークで鮮烈な印象を残したブラジル・アラゴアス州出身のブルーノ・ベルリ。バーラ・デゼージョのドラ・モレレンバウムにベベ・サルヴェゴといった本国のシンガーたちとのジョイント・ライヴ、さらにはFKJのブラジル公演でサポート・アクトを務めるなど、その躍進は止まらない。新たに公開された一曲は、ライヴでも長らく披露されていた、微睡みの最中に放り込まれたような浮遊感のあるフリー・フォーク。同郷の盟友、batata Boyに加え、こちらも《Far Out Recordings》よりアルバムをリリースしているリオの重要人物、アントニオ・ネヴィスも参加している。(風間一慶)
Chanel Beads – 「Police Scanner」
NYのDIYシーンで活動を続けてきたクリエイター、Shane Laversを中心に、ColleことMaya McGrory、ヴァイオリニストのZachary Paulが加わったプロジェクト。ディーン・ブラント以降のエクスペリメンタルな音像と、アーサー・ラッセルを思わせるアヴァンギャルドな手触りを持ちながら、インディー・ギター・アクトとも親和性を感じさせるポップネスが開花している。ハイパーポップやデジタル・シューゲイズのテクスチャーにとどまらないLaversのプロダクションのセンスが感じられる新曲ゆえに、《Jagjaguwar》からのリリースなのも納得。(駒井憲嗣)
flowerovlove – 「a girl like me」
Joyce Cisseのソロプロジェクトであるflowerovlove、本作ではイージー・ライフやアルフィー・テンプルマンなどを手がけてきた元ドッグ・イズ・デッドのRob Miltonがプロデュースを手がけている。この曲を聴いて私が最初に思い浮かべたのが、マッシヴ・アタック「Pray For Rain」だ。本作のキラキラした雰囲気とは対照的な楽曲だが、冒頭からのシンセの音色や「Pray For Rain」のハイライトである後半ブリッジ部分にある解放感あるコーラス・ワークなど共通点が見出せる。この2曲を頭の中でマッシュアップせずにはいられず、何度もリピートしてしまう。(杉山慧)
Mei Semones – 「Wakare No Kotoba」
日本語詞と英語詞をシームレスに行き来しながらネオ・アコースティックなサウンドを奏でるMei Semonesが《Bayonet Records》とサインし、新曲をリリース。変拍子のギター・アルペジオ、弦楽器を交えた繊細なアンサンブルなどマスロック調の硬質なアレンジながらも、甘くナイーヴな歌声とともに淡いパステルカラーの響きがふわりと立ち上がる、その構造と質感のコントラストが印象的。バークリー音大でジャズ・ギターを学び、インディー・ポップからR&Bまで様々なジャンルの音楽家をサポートしてきた彼女の確かな演奏スキルと経験に裏打ちされた表現力のなせる技だろう。MVの冒頭に映り込む大島弓子『綿の国星』からも、Mei Semonesの心の深部を優しく抉るような世界観が垣間見えるようだ。(前田理子)
Ogawa & Tokoro – 「Time & Space」
Ogawa & Tokoroが11月24日にリリースしたアルバム『Mutual Mutation』からのリード・トラック。バレアリック、アンビエントと評される寡黙でスタイリッシュな音像をまといながらも、彼らのサウンドには様式の新しさやユニークさだけにとどまらない、濃厚なエモーションとポップネスを感じる。本曲においてもチルでダビーなバックビートは思考を放棄したくなるほど心地良いが、そこに乗るスライドギターとピアニカ、包み込むような大きなメロディが生み出す、未来形の郷愁とも言うべき感情がそれを許さない。このある種の過剰さに私は新たなポップ・ミュージックとしての可能性を見る、と言ったら大げさだろうか。(ドリーミー刑事)
Porij – 「You Should Know Me」
ポリジはマンチェスターのエレクトロニック・ポップ・バンドで、本曲はプレイ・イット・アゲイン・サムと契約してのファースト・トラックとなる。疾走感のあるドラムンベースに仕立て上げた22年リリースの「Figure Skating」で彼らのことを知ったが、その後もポスト・ダブステップ、オールドスクール・レイヴ、ディープ・ハウスなど、マンチェスターのダンスフロアで鳴らされてきたサウンドを養分にしてすくすくと成長を遂げてきた。カラフルかつ変化に富んだ本トラックは、そうした音楽背景を巧みに編み込み、徐々に自分たちのスタイルを確立させてきている過程を描き出している。(油納将志)
Yaeji – 「easy breezy」
曲を聴きながら“It’s not so easy, it’s not so breezy”と口ずさんでいれば自然と力が抜けてくる。柔らかい風やぽかぽかの太陽が似合うボサノヴァ風味のギターと、弾ける小さな波のようなドラムンベースのビート。仕事のイライラもわかり合えないさみしさもさらさら飛んでいく。今年4月のアルバムと比べたらリラックスした気持ちで聴ける楽曲であることに違いないが、歌われているのはアルバムと地続きとも言える、望まなかったことの伝え方や自分自身を抑圧しないこと。どれも簡単ではないけれど、どれも考えないとね。時間という解決策もあることや、つぶらな瞳のバナナのコアラにくすっと笑える気楽さも忘れずに。(佐藤遥)
柴田聡子 – 「白い椅子」
アレンジやミキシングに岡田拓郎、マスタリングにDave Cooleyらの名前が目を引くクレジットのシングルは2枚目となるが、これまでと空気が違う、重要なピースになりそうな一曲。歌詞に登場する花屋は実際に自宅近くにあり、「その店主とは相性が悪く…」とは本人コメントの通りもはやシグネチャーと言える描写の妙に、今回は柴田聡子流の「冷たさ」が漂う。呼応して重く絡みつくファンクネスもクールで新鮮、しかし必然的な変化であると妙に納得できるのは、前作『ぼちぼち銀河』をあらためて聴くと、すでにその萌芽を感じる瞬間もあるからだろうか。来たるニュー・アルバムに向けて、この曲がどんな意味を持っていくのか楽しみだ。(寺尾錬)
ゆるふわギャング/踊ってばかりの国 – 「君の街まで」
《JOURNEY RAVE》で披露したこのコラボが話題だったが、さらに精度を高めて満を持して発表された。EP全体を通して、バンドサウンドの上に置いたとき、3人のひと癖ある声がこんなにも協調していたことに気づかされる。楽曲の内容について、今はもう会えない人と会えてしまうユートピアのような場所は、確かに存在すると考える。本質は会いに行く行為や会える場所であって、肉体が人間の全てでないのかもしれない。人の存在がいかに不確実なものであるかというサイケ調な歌詞(リリック)と、バンドの上にある声から2組の親和性により納得するのだ。最近では、《全感覚祭》に出演していたことが記憶に新しいが、一部の界隈のみの活動にとどまらない印象の彼らの存在は、ジャンルをもゆるりと超えてゆく、実態のない煙のようなものではないだろうか。(西村紬)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Haruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiRiko MaedaNana YoshizawaIkkei KazamaRen TeraoTsumugi NishimuraDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoKei SugiyamaDaiki TakakuYasuyuki Ono