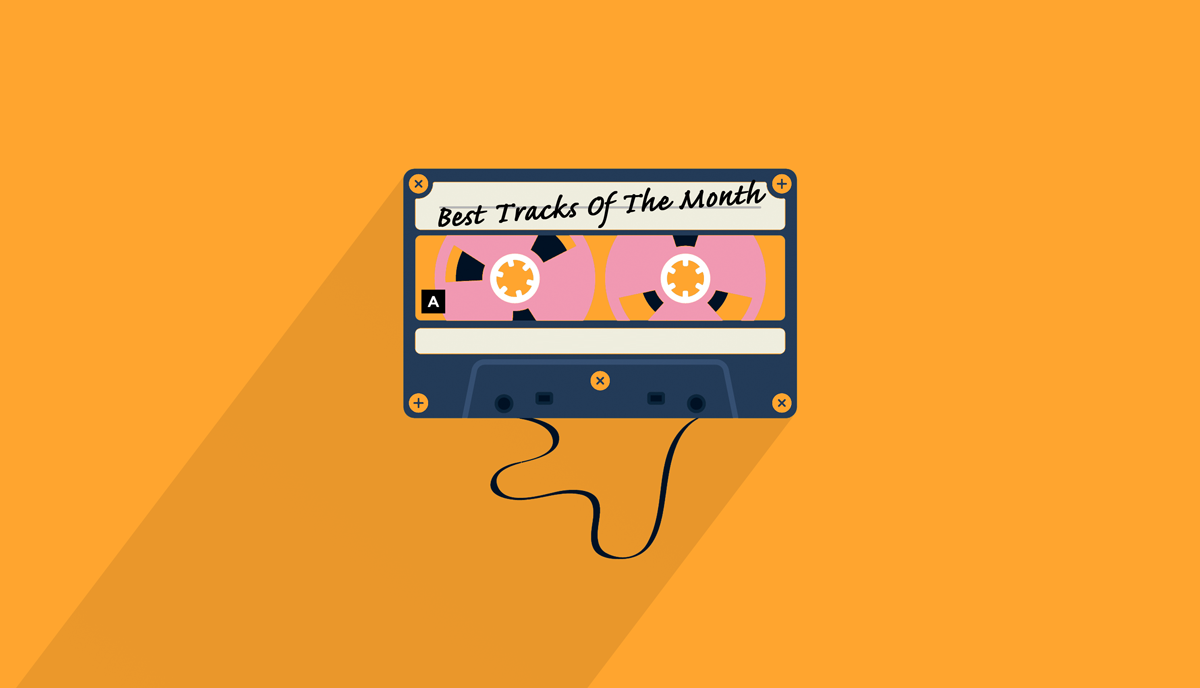BEST 11 TRACKS OF THE MONTH – July, 2022
Editor’s Choices
まずはTURN編集部が合議でピックアップした楽曲をお届け!
Bobby Shmurda – 「Hoochie Daddy」
「Hoochie daddy」とは、太ももを大きく露出するショートパンツを履いた男性を指すミームなのだそう。ボビー・シュマーダは、複数の容疑による6年の収監から昨年釈放されたブルックリン・ドリルの先駆者。なのだが、この楽曲ではフットワークとドラムンベースとジャージー・クラブが渾然一体となった高速ビートにのせて、「オレはhoochie daddyじゃねーっ!」と飛ばしまくる。でも、ジャージー・クラブ特有のベッドが軋むキコキコ音に合わせて腰をくねらすMV、蛍光塗料を流しこんだようなアートワーク、リリック、そのすべてが呼びおこすのは強烈にセクシャルで「ホット」なイメージ。欲求を貪るようにまくしたてる彼のフロウも享楽的。(髙橋翔哉)
Campanella, GuruConnect – 「Bell」
skillkillsのブレイン、スグルスキルとしても知られるGuruConnectと東海の雄、Campanellaによるシングル。パーカッシヴにアンビエンスと共に跳ねるトラック。ラップのリズムが重なってドライヴする空気。描かれているのは、ある一夜のパーティー、あるいは祝祭の情景。パトワ語に、「生ダラ」に、「ホンダベイビー」。つまり、レゲエ、とんねるず、FKAツイッグス? 交錯するコンテクスト。スピーカーから流れる爆音で途切れ途切れに繰り返される脈絡のない会話のように。音と言葉。連なって、波打って。揺れる思考、揺れる身体。ハイに、灰に。煙とアルコールと汗。瞬間のカオスを掴み取る、二人の剛腕。(高久大輝)
Macie Stewart – 「Maya, Please」
シカゴ拠点のシンガーソングライター/コンポーザー/マルチインストゥルメンタリスト、マーシー・スチュワートによる新曲。フィンガー・ピッキングにより奏でられるアコースティック・ギターと重厚に響くストリングスの音色が、アンビエントなフォーク・サウンドと淡白なメロディー・ラインのなかに鮮やかな彩りを与えている。昨年にリリースされたアルバム『Mouth Full of Glass』同様に、本曲も近年アンビエント・フォーク関連の佳作を立て続けにリリースしているシカゴの新興インディー・レーベルである《Orindal Records》からのリリースとなっている。(尾野泰幸)
Movulango – 「Other Way」
今年に入ったあたりから、シャーロット・アディジェリーなどの新世代とコンゴ出身のマリー・ドルヌを中心とするザップ・ママあたりとを繋げて“アフリカ移民の文化としてのベルギー音楽”を検証しているのだが、ヘントを拠点とするこのMovulangoも新たな動きを後押しする重要アーティストになりそう。昨年リリースされたソウルワックスのレーベル《Deewee》のコンピにも参加していたが、この新曲はクラウト・ロック、シンセ・ポップ、サイケを幻想的に混在させ、ちょっとスクリッティ・ポリッティのグリーンのような甘さのあるヴォーカルで包んだような曲。8月に入ってもう次の曲が公開に。ベルギーは予想以上に進化の速度が早い。(岡村詩野)
Writer’s Choices
続いてTURNライター陣がそれぞれの専門分野から聴き逃し厳禁の楽曲をピックアップ!
boy pablo – 「Be Mine」
boy pabloことPablo Muñozは、ノルウェーのベルゲン出身だが、両親は南米チリにルーツを持つSSW。Cucoとの「La Novela」は、そうした彼のルーツを強く感じさせる楽曲だった。直近ではヒューマン・リーグ「Don’t You Want Me」をカバーするなど、活動を活発化させている。本作は、Cuco「Paradise」と聴き比べると面白い。どちらも夕陽が沈むビーチが似合う楽曲だが、ダウナーなCucoに比べ、こちらはトロピカルに彩られた陽気な楽曲で、さらに80年代を彼の中で再解釈した先のカバーの延長と言える楽曲でもある。彼が次のフェーズに入ったようで、そこも注目だ。(杉山慧)
South Bad Boy – 「Erica」
2020年初EP『South Flavor』でソングライティングの卓越ぶりは折り紙付きだったSouth Bad Boyだが、近年目立った活動は散発的なライブ出演のみだった。念願の新音源『That’s All I Can Hope For』の一曲「Erica」では麗しいポップ・センスが健在であることを存分に聴かせてくれる。甘い歌詞とセンチメンタル・ムードたっぷりの中に響く落日飛車の影響色濃いサイケデリックなギターのトーンが実に微笑ましい。長渕剛「順子」やデレク・アンド・ザ・ドミノス「Layla」と歴史が証明しているように、タイトルに女性名を冠すると不思議と名曲にならざるを得ないようだ。(Yo Kurokawa)
Gilla Band – 「Eight Fivers」
前作『The Talkies』は、バンドの旧来的なフォーマットを解体し、鈍器で殴られたような凶暴なサウンドと、ブレグジット前の英国恐怖症(Anglophobia)が叫ばれる時期に、すべて回文のリリックで構成した「回文恐怖症(Aibohphobia)」なる曲を収録するアイロニカルなセンスも抜群だった。改名後初のシングルは、「クソみたいな服に金を注ぎ込んだ」というイントロそしてローカルなスーパーの店名が連呼されるコーラスへの流れが痛快。ポスト・パンクというよりもテクノやインダストリアルのそれに近いプロダクションは、マシーナリーな度合いを増している。意味をかなぐり捨てる叫びに近い歌とサウンドが、捨て鉢ではなく内省に向かう点が彼らの魅力だ。(駒井憲嗣)
Jasper Tygner – 「92」
ノース・ロンドン出身のJasper Tygnerは、2020年にデビューしたプロデューサー。《Shall Not Fade》や、レフトフィールドなレーベル《Needwant》などからリリースを重ね、ロンドンのアンダーグラウンド・シーンを牽引する存在だ。VegynやRoss From Friendsと、Two Shellやyunè pinkuの間に位置していると見ている。このシングルは、夏の夕方、涼しめの気温に合うディープ・ハウス。4月に出したEPより全体的に控えめな低音と、シンセのメランコリーな質感が、レイヴ・ミュージックへの敬愛を感じるメロディの陶酔感を増幅させている。今年のわたしのサマーアンセム!(佐藤遥)
Marci – 「Pass Time」
インディーポップの隠れたメッカであるモントリオールにおいて、TOPSがどれほどの貢献をシーンにもたらしてきたかは言うまでもない。しかしキーボーディストであるMarta Cikojevicの加入がTOPSのサウンドをレトロに肉付けし、そのソロ・プロジェクトであるMarciが80’sリバイバルの最適格であるほどに素晴らしい、というのは未だ満足には追求されていないようだ。デビュー作『Marci』からの先行曲「Pass Time」での、固い頭韻の踏み方ひとつで時代感を提示できるのは、彼女がソングライターとしてもレトロ志向であることを伺わせる。オルガンブレイクを緩衝装置として曲のムードが遷移していくのも見逃せない。(風間一慶)
サニーデイ・サービス- 「冷し中華」
2020年の『いいね!』以降、久々のフィジカルリリースとなるサニーデイの新曲。まず聴こえてくるのはフォーキーでエバーグリーン、そしてどこかアジアの香りが漂うグッドメロディ。まさに暑中見舞いのようなさりげない親しみ。しかし4分を超えた頃から始まる2分以上に及ぶ長いアウトロに突入すると様相は一変。鈍行列車だと思っていた電車は実は銀河鉄道だった!というくらいにコズミックでプログレッシブな展開を見せていく。この曲は曽我部恵一が高速道路で見た夕陽にインスピレーションを得て、サービスエリアで書き上げられたそうだが、この日常の光景と深遠なる宇宙を接続させる想像力こそが彼の表現の源泉であることが伝わる一曲だ。(ドリーミー刑事)
Rory Aaron, Antony Szmierek – 「Keep It Simple」
マンチェスターのラッパー/コンポーザーのアントニー・スミレクと、ダービー生まれでマンチェスターを拠点にする劇作家、詩人、ラッパーとして活動するロリー・アーロンとタッグを組んだシングル。ザ・ストリーツやバイセップからの影響が伺えるミニマルなトラックの上をクールなスポークンワードが滑り出す「The Hitchhiker’s Guide to the Fallacy」でアントニーの存在を知ったのだが、このコラボも彼がサウンド面で主導となり、ロリーとスポークンワードを対話するように交わし合う。ロイル・カーナーの新曲「Hate」やケイ・テンペストの「More Pressure」との共通項も見出すことができ、ポスト・レイヴ的なサウンドがひとつのスタイルとして定着しつつあることも実感する。(油納将志)
【BEST TRACKS OF THE MONTH】
過去記事(画像をクリックすると一覧ページに飛べます)
Text By Yo KurokawaHaruka SatoKenji KomaiShoya TakahashiIkkei KazamaDreamy DekaShino OkamuraMasashi YunoKei SugiyamaDaiki TakakuYasuyuki Ono