【未来は懐かしい】Vol.17
近年再注目を集めるブラジル地下音楽シーンに残された、
エクスペリメンタル/アヴァンギャルド名盤が再登場
70年代後半から、90年代初頭にかけてのブラジル地下音楽シーン。そこには、最近になるまでごくコアなマニア以外からは目を向けられることのなかった秘宝的作品が数多く存在する。MPBでも、一時期DJ視点から注目されたサンバホッキでも、もちろんボサ・ノヴァでもない、そうした「非主流」のブラジル音楽が注目される大きなきっかけとなったのは、オランダの再発レーベル《Music From Memory》が2017年に発売したコンピレーション・アルバム『Outro Tempo: Electronic And Contemporary Music From Brazil, 1978-1992』(2017年)だったと言えるだろう。アンビエント、ミニマル等、様々な要素に満ちた「知られざる」トラックを編纂したそれは、それまで一般に抱かれていたブラジル産音楽に対する見取り図/理解を決定的に更新することになった。
また、こうした発掘の動きを、情報アーカイブという側面から盛り上げた著作の存在があった。それが、評論家ベント・アラウージョが監修を務めたレコード・ガイド『Lindo Sonho Delirante』シリーズだ。かねてより世界中のディガーが注目してきたブラジル産サイケを主に特集した第1弾も労作だが、ここでの文脈でより重要なのは、1976年から1985 年までのアンダーグラウンド作品をレビューする第2弾(2018年刊)だろう。このシリーズは現在も継続しており、軍事政権終焉後の1986年から2000年までをカバーする第3弾の刊行が先だってアナウンスされるなど、ブラジルのアンダーグラウンド音楽の掘り返しというのが、今まさに注目すべき潮流となっているのだ。
今回紹介するジョアン・ヂ・ブルソー&R.H.ジャクソンによる作品『Caracol』(オリジナル発売:1989年)のリイシューは、こうした関心の高まりを象徴するような出来事といえるかもしれない。
ジョアン・ヂ・ブルソーは元々ドラマーとしてジャズやフォホー(ノルデスチ発祥のダンス音楽)の演奏からキャリアをスタートさせたパーカショニスト/マルチ楽器奏者で、それまでは舞台やテレビ番組などのプロダクション・ミュージック制作にも関わっていた人物。方やR.H.ジャクソンも、ドラマー/パーカショニストとして活動を開始、USに渡った後専門的なプログラミング/エンジニアリングを学び、電子音楽を軸にサウンドトラック制作などを行う傍ら、フォークロア研究者としても活動していた人物だ。本作はそんな二人がコラボレートした唯一のレコードで、お互いの経歴から想像される通り、非ポップス的で、なかなかアヴァンギャルド色強い内容となっている。
ジョアンが操るのは、各種パーカッションや、アコーディオンをはじめ、銅製の花瓶、動物の蹄、マグカップといった日用品からおもちゃの楽器まで、実に多彩だ。ジャクソンは、ギターに加え、主に電子音のプログラミング、サンプリング、イコライジングを担当している。今回のリイシューLPに付属のライナーノーツ(執筆を担当したのは上述のベント・アラウージョ)によれば、通俗的なブラジル音楽(同国のポップス)に特徴的なクリシェをいかに排するかということへ相当意識的に取り組んだという。たしかにここには、楽曲構成やハーモニー、リズムにしても、MPBなどの今現在連想される「ブラジル音楽」的な要素は希薄で、むしろ全体の印象としては、ポスト・パンクやダブの方法論を通過した後に出現した、同時代の西欧産の(疑似的な)いわゆる「ワールド・ミュージック」と近いものも感じる。一方で、反復するミニマルなフレーズや各種パーカッションが先導するトライバルな表情は、ポピュラー音楽覇権の時代を飛び越えて遡り、より原初的な、民族音楽/フォークロアとしてのブラジル音楽へ直接接続するような瞬間を頻繁に演出する。
個人的な注目曲をいくつか挙げてみよう。A2「Dona Roxa」は、メイン・リフを奏でる硬質なデジタル・シンセサイザーのサウンドがいかにもこの時代ならではという感じで好ましい。その上を走行するのは、まるでテリー・ライリー「A Rainbow In Curved Air」がごとき清涼なフレーズで、全体としてかなり珍妙。B1「Here We Go Again」は、80年代前半のUK産ポスト・パンク〜インダストリアル・ミュージックを思わせるけたたましくいビートに支えられながらノイジーなギターやパーカッションが回遊する比較的キャッチーな曲。先述のコンピ『Outro Tempo〜』へ収録されたB3「Terra Batida」は、ガムランを想起せざるをえない(銅製の花瓶?)の連打と、奥深いアマゾンに響く類人猿の鳴き声(的なエスニックな意匠)が混じり合うミニマルなトラック。他にも、アヴァン・ポップ〜トイトロニカ風のB2「Cabarecht」、“酔っ払ったデメトリオ・ストラトス”とでも表現したくなる奔放なヴォーカリゼーションを聴かせるB4「Caracol」など、個性的な曲ばかりだ(今回の再発にはオリジナル未収録のボーナス・トラック2曲が加えられており、そちらも本編に劣らず刺激的)。
特定のカテゴリーへの埋没を念入りに拒否するかのごときこうした折衷性というのは、二人の述懐によれば、アカデミック/理知的に構築されたものというよりも、あくまで即興的な制作作業の中から自然に表出してきたものらしい。ときには、コンピューターの暴走によって偶然生まれたシーケンスやフレーズをそのまま採用しているトラックもあるという。 コンセプトを措定しながらも、同時に偶然性を呼び込もうとする。その2つが見事なバランスで結実したのが本作ということだろう。自国の音楽文化の重層性を自覚しながらも、その重力に逆らって跳躍してみせる。いわばこれは、ポスト・パンクの時代を通過したブラジルで生まれた、再帰的=リ・オリエント的アヴァンギャルド音楽というべきか。
当時の音楽家達による鋭い視線/制作理念が再提示され、そこから現在へ向けた思考が焚き付けられるというのも、優れたリイシュー作品に触れるときの面白さだ。(柴崎祐二)
Text By Yuji Shibasaki
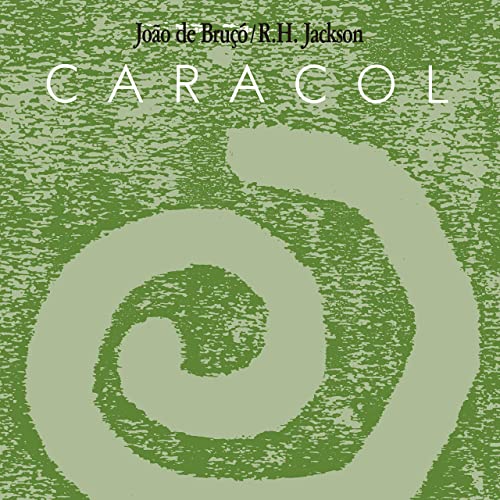
João de Bruço / R.H. Jackson
『Caracol』
2020年 / Discos Nada (レコード/配信)
オリジナル・リリース:1989年
購入はこちら
Tower Records / Amazon / HMV / disk union
柴崎祐二リイシュー連載【未来は懐かしい】
アーカイヴ記事
http://turntokyo.com/?s=BRINGING+THE+PAST+TO+THE+FUTURE&post_type%5B0%5D=reviews&post_type%5B1%5D=features&lang=jp
