寒空のマンチェスターとマイアミの太陽の幸せな邂逅
ニュー・オーダー Miami Residencyを振り返る
2020年1月14、15、17、18日、フロリダ州南部のマイアミビーチ市でニュー・オーダーは(以下NO)は4回にわたるレジデンシー公演を行なった。1950年にオープンした会場の《フィルモア・マイアミ》はコメディアンで俳優のジャッキー・グリーソンの名が付された劇場を有し、高い天井とシャンデリアがブロードウェイの劇場を彷彿させる。1月のマイアミビーチ一帯は比較的湿度も低く、ヴァカンスにうってつけの温暖な気候だ。マイアミの青い空とココナツの木やハイビスカスは、ジョイ・ディヴィジョン(以下JD)の楽曲やNOの初期2枚のアルバム(『ムーヴメント(Movement)』『権力の美学(Power, Corruption & Lies)』)のくぐもったイメージとはだいぶ違う世界のはずだ。寒空のマンチェスターとマイアミの太陽は正反対といってもよいだろう。筆者は第一夜を観るまでマイアミで聴くNOおよびJDがいったいどんな体験になるのか想像もつかなかったが、ショーの内容だけでなく、マイアミビーチ市とNOとの友好関係、米国内外から集まったファンたちの様子などをとおしてNOのマイアミ・レジデンシーをふり返ってみたい。
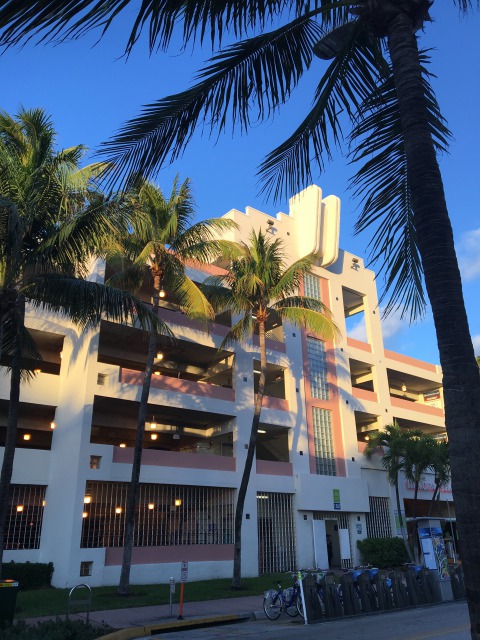 マイアミビーチ市のアール・デコ歴史地区。1920〜30年代に建てられたホテルやアパートメントが並ぶ。
マイアミビーチ市のアール・デコ歴史地区。1920〜30年代に建てられたホテルやアパートメントが並ぶ。
 フィルモア・マイアミ
フィルモア・マイアミ
 会場に並ぶ人々
会場に並ぶ人々
 バー・カウンターではNOにちなんだカクテルが売られていた。
バー・カウンターではNOにちなんだカクテルが売られていた。
各日ともNOのリミックスやプロデュースを手がけたアーサー・ベイカーがDJを2セット行った。彼の選曲は近年のエレクトロニカから80年代のニュー・ウェイヴやディスコ・チューンに及ぶまで幅広く、特にペットショップ・ボーイズが流れ出した瞬間、会場がどよめくほど盛り上がった。感極まった筆者は日本にいる友人に「さっきアーサー・ベイカーがペットショップ・ボーイズをかけていました」とメッセージを送ったほどである。オープニング・アクトを務めたのは、1月14、15日が地元出身のバンド、Donzii。今回はDonziiのメンバーの他にボンデージ衣装に身を包んだ謎のパフォーマーも登場した。彼女は演奏行為には一切関与せず、ステージでシャンパンの瓶を振り回すなど極めて自由に振る舞い観客を煙に巻いた。1月16、17日は80年代のディスコとファンク・シーンを牽引したRockers Revengeと彼らのプロデューサーでもあるアーサー・ベイカーが共演した。
《∑(No,5m,20Mia)》と題された初日(1月14日)は、12人のシンセサイザー・オーケストラと共演した2017年のマンチェスター・インターナショナル・フェスティヴァル(MIF)での《∑(No,12k,Lg,17Mif) New Order + Liam Gillick: So it goes …》を踏襲しつつ、今回のレジデンシーに際してNOのメンバー5人だけの編成に再構成したステージだった。「Times Change」のインストゥルメンタル版でレジデンシー初日が幕開けた。この時一緒に映し出された映像は、白や青の外壁のホテルやアパートメントが建ち並ぶマイアミビーチ南部アール・デコ地区の1960年代、1970年代の風景を素材にしたものだ。この郷愁誘う風景と「Times Changes」が妙に合っていて、筆者はマイアミビーチとNOとの組み合わせに納得してしまった。
その後、メンバーが登場。最初の数曲は「Who’s Joe」「Dream Attack」、「Disorder」(JD曲)、「Ultraviolence」、「Heart and Soul」(JD曲)、「All Day Long」といった、打ち込みよりも生演奏を主とする楽曲が並ぶ。「Shellshock」からは一転してNOのダンス系の曲を新旧織り交ぜた構成に。「Subculture」、「True Faith」、「Blue Monday」など、ここから明らかにNOが観客を躍らせようとしている。正直に告白すると筆者は今まで「Blue Monday」にそれほど愛着を抱いておらず、むしろ他の曲の方が好きだったが、今回マイアミでの「Blue Monday」の盛り上がりを経験してみて、この曲に対する認識を改めた。「Blue Monday」で踊るのは楽しい経験だ。シンプルなパターンながらもリズム・マシンを駆使したダンス音楽としてよく構成されているだけでなく。NOの持ち味の一つである暗さもしっかり維持している点に、筆者はこの曲の偉大さを今さら見出した。この日は定番「Temptation」で本編が終わり、アンコールはJDの「Decades」と「Love Will Tear Us Apart」の2曲。今、JDの曲をNOの演奏で聴くことはミサのような儀式的な意味をも持つのではないだろうか。
4日間のセットリストは基本的に上述した構成(JDとNOのロック系楽曲、『Low-life』と『Technique』の曲を主としたNOのダンス系楽曲、JDの楽曲で大団円)だが、セットリストを振り返ってみるとどの日もその日限定の曲が必ず数曲入り、アンコールも含めて4日間全て違う内容だった。
マイアミビーチ市は2日目にあたる1月15日を『New Order Day』と定めた。オープニング・アクトの後、その贈呈式がマイケル・ゴンゴーラ市議会議員によって行われた。ニュー・ウェイヴ音楽を敬愛するゴンゴーラ氏はこれまでのNOの音楽界への献と、マイアミを彼らの米国でのレジデンシーの地に選んだことへの感謝を述べた。彼は“I think every day should be New Order Day.(毎日がNew Order日でないといけない)”とも言い、この言葉に筆者は全面的に同意する。
3日目、筆者は劇場2階のバルコニー席でショーを俯瞰した。ステージ前にいると気付かなかったのだが、現在のNOのショー照明による舞台演出にとても力を入れていることがわかった。ここでの照明はステージを照らすのみならず、劇場高方の空間に光の幾何学的なパターンを照射していた。たとえステージ前方に位置取らなくとも楽しめる要素を見つけることができた。また、この日は観客の様子も観察していたのだが、スマホなどを一切手に取らず、とにかく踊る人々が少なくなかった。体を揺らす程度の人もいれば、時々ターンも織り交ぜてダイナミックに踊っている人もいた。NOはダンス音楽でもある。これらの光景はこの基本事項を思い出させてくれた。
1月18日、筆者はステージ前に戻って最終日を満喫した。この日は「Regret」で始まり、本編最後の「Temptation」まで観客も終始高いテンションのままだった。ステージ前方の場所取りは時に苛烈な様相を呈するが、今回、筆者が印象に残ったのはステージ前が必ずしも戦場のような場所の取り合いになっていなかったことだ。誰からともなく背の小さい女性を前方の方に誘導する光景もいくつか見られた。これは筆者が偶然目にしただけの出来事なのかもしれないが、観客同士が譲り合ってハッピーな時間と空間を共有できたことは確かである。
前述のとおり、最近のNOのショーは映像や舞台演出がさらに洗練されている一方、フロントマンのバーナード・サムナー(以下バーニー)が今でもたまに演奏が危なっかしくなる瞬間を見せてくれるので、昔からのファンはそんな様子に少し安堵するかもしれない。マイアミと同じ演出で日本公演が行われるかどうかわからないが、マイアミでは途中、バーニーが前方の観客にマイクを向けて曲の一部を歌わせるシンガロングが何度か起きた。彼にいつマイクを向けられても動揺せずに済むよう、NOを観に行くファンはせめて「Temptation」、「Bizarre Love Triangles」くらいは元気に歌えるようにしておきたい。
1月14日の「Bizarre Love Triangles」でのシンガロングの様子。
1月18日の「Temptation」でのシンガロングの様子。
最後にTシャツについて触れておこう。もちろんマイアミでも多くの人々がJD『Unknown Pleasures』と『Closer』、NOの『Power, Corruption & Lies』や『Movement』をはじめとするアルバム・ジャケットのTシャツを着ていた。『Unknown Pleasures』に関してはアラビア語や日本語ヴァージョンを着ている人もいた。今では入手困難と思われる80年代のツアーTシャツなど、マイアミに歴代のほぼ全てのJDとNOのTシャツが集結したのではないかと思えるほどだった。Peter Hook &The LightのTシャツの人も毎回必ずいて、筆者は他人事ながらいらぬ心配をしてしまった。マンチェスターにちなんでなのか、The Smiths、モリッシー、ジョニー・マーTシャツの目撃頻度も低くなかった。結局は自分の好きなものを着ればよいわけだが、デザイナーのピーター・サヴィルによるアートワークがバンドのトレードマークとなっているNOのライヴ会場では、観客が身に着けている様々なデザインのTシャツを観察するのも楽しみの一つだといえる。
この原稿を書き上げてからしばらくたった2020年2月26日、新型コロナウイルス感染症の影響により、3月に予定されていた東京と大阪公演の延期が発表された。既にチケットを持っていたファンはこの事態をある程度覚悟していたはずだ。筆者も過度に落ち込まないように心の準備はできていたが、やはり事実に直面するとやるせない気持ちになるのが正直なところである。この状況をポジティヴな思考に転じるならば、バーニーにいつマイクを向けられてもよいように、上述した楽曲の歌唱を日本のファンが完璧になるまで練習する時間が増えたのだ。そう思いながら、彼らが来日する日を気長に待つことにしよう。
現在もコンサートその他イヴェントの中止や延期が続々とアナウンスされている。私たちがかつてのように場所を共有できるようになるにはしばらく時間がかかるかもしれないし、もしかしたら、この状況が収束した先には今までとは違うライヴ・カルチャーのあり方が生成されるかもしれない。今まさに私たちがその過渡期にいることは間違いないだろう。(文・撮影/高橋智子)

Stage Photo by Warren Jackson

Text By Tomoko Takahashi
